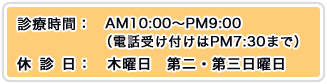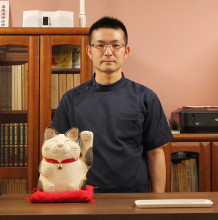梅雨の時期の不調 湿邪
・全身が重だるい
・疲れやすく、なかなか疲れが取れない
・足が重い
・むくみやすい
・肘や膝など関節が痛くなる
・食欲がなくなった。
この症状、もしかすると邪が原因の症状かもしれません!
○湿邪(しつじゃ)とは
東洋医学では病気の原因を病因といい、カラダの外側からくる病因を外因、カラダの内側から生じ、過度の感情が原因となる内因、外因にも内因にも属さない不内外因の3つに大きく分けられます。
湿邪は外因に属し、湿度が高い中で生活している他に、濡れたものを長時間着ている、水中で作業する、雨にあたることも湿邪の要因となります。
梅雨に入って気温と湿度が高くなると、体は熱くても充分に汗をかくことができず、汗とともに出て行くはずの水分や老廃物がたまりやすくなってしまいます。
○湿邪の性質
湿邪にやられたカラダは、余分な水分を溜め込んでいる水分代謝が悪い水太り体質状態です。
粘り気や濁りという性質を持っているので体内に侵入すると、代謝や気の流れを停滞させ、体の倦怠感、関節痛、下痢、むくみ、胃腸の不調を発生させます。
四肢を動かすのが重だるくなったり、病気の治りが遅くなったりもします。
○湿邪を解消するためにできること
ここでセルフケアをあげたいと思います。
①汗をかくこと
外は暑いからと言って外出をひかえ過ぎていると体内に湿が溜まりやすくなってしまいます。
軽い運動などをして汗をかくようにしましょう。
ただし、体力が弱い方が汗をかくほどの運動をすると、反って体調が悪くなることがあります。
その場合は、無理をせず休養を取り、胃腸の調子を整えて体力をつけるといいでしょう。
②体を冷やさない
クーラーなど冷房機器を使うこの時期は、意外と体を冷やしやすいです。
体が冷えると、代謝が悪くなり汗もかかなくなるので、結果湿邪が溜まってしまいます。
特に下半身を冷やさないようにして、着るもの、食事、入浴に気をつけましょう。
③食事に気をつける
胃腸(東洋医学でいう脾胃)は湿に弱いです。
湿気が多い時期は、胃腸の働きも悪くなりやすく胃もたれ、下痢になりやすい時期です。
食中毒にかかりやすいのもそのためとも言えます。
なので、なるべく消化に良いものを取ることが大事になります。
タイプ別おススメの食材
・水分代謝の悪い人(頭痛・吐き気・食欲不振・頭重・むくみ)
ごはん・長芋・かぼちゃ・ナツメ・さつまいも小豆・そら豆・はとむぎ・とうもろこし
・四肢が冷えやすい人(下痢・腹痛・むくみ・関節痛)
生姜・ネギ・とうがらし・にんにく・にら・海老
・熱がこもっている人(熱がこもる・のどが渇く・口臭・にきび・重だるい・頭痛・腹部膨満)
冬瓜・にが瓜・トマト・きゅうり・大根・こんぶ
甘い物にはカラダを冷やし水分を欲する性質があるので、なるべく甘いものを避けることも大切なことです。
ビールなどおいしい時期ですが、飲みすぎると体を冷やし滞らせる原因になるので注意しましょう。
○鍼灸院・至では
当院では、湿邪にやられているかどうかを問診、脉診(みゃくしん)をすることにより判断します。
もし湿邪が原因の体調不良の場合は、湿邪に対して有効なツボに鍼灸刺激を与え、カラダから除去する手助けをします。
もし、梅雨の時期になると必ず体調が悪くなる。雨の日は体調がすぐれない。ようなことがございましたら、ぜひ鍼灸治療を受けてみてください。
鍼灸院・至
http://89-itaru.com
住所:神奈川県川崎市多摩区生田8-8-9
光シャンブル生田1F
TEL:044-322-8779
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇